マイホーム購入の予算決め。住宅ローンについて。
予算を決めるには、いくつかのポイントをしっかり理解しておかなければいけません。
私たちは、以下のポイントで予算を決めました。
目次
ローンについて
ローンの期間について
基本的には、65歳での返済を考えてローンを組むのが良いでしょう。
65歳 ➖ 現在の年齢
例 35歳の場合 30年ローン
となります。
返済額について
①収入から1ヶ月の返済可能額を算出する。
頭金と借入金から算出すべきです。
年収 ✖️ 25パーセント
例 700万 = 14.5万
オススメは20パーセントを頭金と言われているが、現在はマイナス金利のため住宅ローン控除を受けた後一気に返済した方が賢い選択かと思われる。また、その期間投資信託等で運用しても良い。
②維持費等を除いた金額を出す
借りる金額を決定する
上の金額 ➗ 100あたりの返済額 ✖︎ 100万円
650万だと4200万ぐらいか
③自己資金を足して総予算を出す
頭金はゼロでもいいが、控除後に繰り上げ返済できるようにしたい
私達であれば4500万円台となった。
諸経費について
諸経費がかかることを忘れずに
大体5-8パーセント
最初にかかる諸経費
- 印紙税
- 登録免許税
- 司法書士報酬
- 不動産取得税
- 融資手数料
- 住宅ローン保証料
- 火災保険
- 団体信用生命保険料
- 引越し料金
購入後に年間でかかる経費
- 固定資産税
- 都市計画税
ポイント
諸経費は別途自己資金で用意がベスト
諸経費ローンは金利が高めのため。
その他の支出について
ローン返済以外の支出
- 固定資産税
- 修繕費
- 管理費
ポイント
修繕積立金は1m 202円が一般的
ローンについて
ローンの種類
調べ方
おすすめのローン
私達の場合
団信について
団信とは
団信の種類
住宅ローン控除について
繰り上げ返済は結局得なのか損なのか
特に金利1パーセント以下の変動なら、控除が1パーセントのため、おとく!!!
他の人がどんな年収でどこまでかりているのか
http://minnanoloan.com
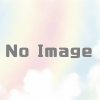
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません